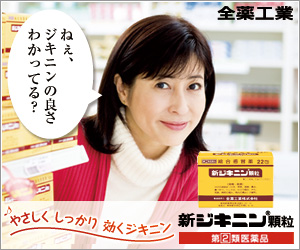- TOP
- >
- 炭水化物制限ダイエットは果たして危険なのか?日本糖尿病学会が提言
新着ニュース30件
2013年3月21日 16:00
糖尿病の解決を食事療法でする
日本糖尿病学会が、糖尿病に対する食事療法について、提言を行った。それによると、炭水化物を極端に制限して糖尿病の食事療法を行うことは、長期的な食事療法としては遵守生や安全性などの点で薦められないとしている。以下、提言を要約した物である。
日本人の食生活は第2次世界大戦後、欧米文化の影響を受けて大きく変化している。国民健康・栄養調査の結果によると、日本人の総エネルギーは1840カロリーまでに減った。その原因は脂質の摂取の増加にあるとされ、逆に炭水化物の摂取は減少の傾向にある。
例えば、最長の寿命として知られていた沖縄県は、その地位を守りきるきることができなかった。原因は脂質の摂取の増加にあるとされ、日本の食生活の変化の影が垣間見られる。
また、食生活だけでなく、日本人の運動不足も問題視されている。行き届いた交通の便、生活の豊かさが引き起こした新しい問題と言える。
これらの問題が引き金となる糖尿病が第2型糖尿病といわれる。インスリンの分泌の低下が問題となりやすい体質の人が、このような問題により内臓脂肪蓄積肥満になる。このことにより、インスリン抵抗性状態が発生する。
食事と運動
第2型糖尿病は、食事療法と運動療法が重要である。食事は総エネルギー摂取量のバランスをとることが目的とされる。または合併症などの予防にも注意を払い、三大栄養のバランスをとつことが必要である。三大栄養とは炭水化物、たんぱく質やエネルギーである。合併症としてあげられるのは、動脈硬化性疾患、糖尿病腎症などの臓器障害である。
また、炭水化物などだけを極度に摂取の減少させる方法は、長年の追跡調査の結果、あまり効果がないとされた。総エネルギー量摂取の減量が鍵となる。
日本糖尿病学会が発表した「糖尿病ガイドライン」がある。この中では、たんぱく質の摂取は体重1キロに対して1gから1.2g(50g〜80g/日)と限度が設けられている。
たんぱく質の上限の考慮は、肝臓への負担考えたものである。その他、食物繊維は日に20g以上を摂取の目安とする。
根気よくつづける食事療法
このような食事制限療法は、医師の指示のもとで行うことが重要とされる。そして、病状や食事の嗜好にあわせて楽しんで食事ができる体制をとることが重要である。長期間にわたって継続しなければ効果を発揮されないので、よりよい食事療法を実践しつづける必要がある。
日本人の糖尿病の食事療法に関する日本糖尿病学会の提言
http://www.jds.or.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php
-->
記事検索
アクセスランキング トップ10
特集
お問い合わせ